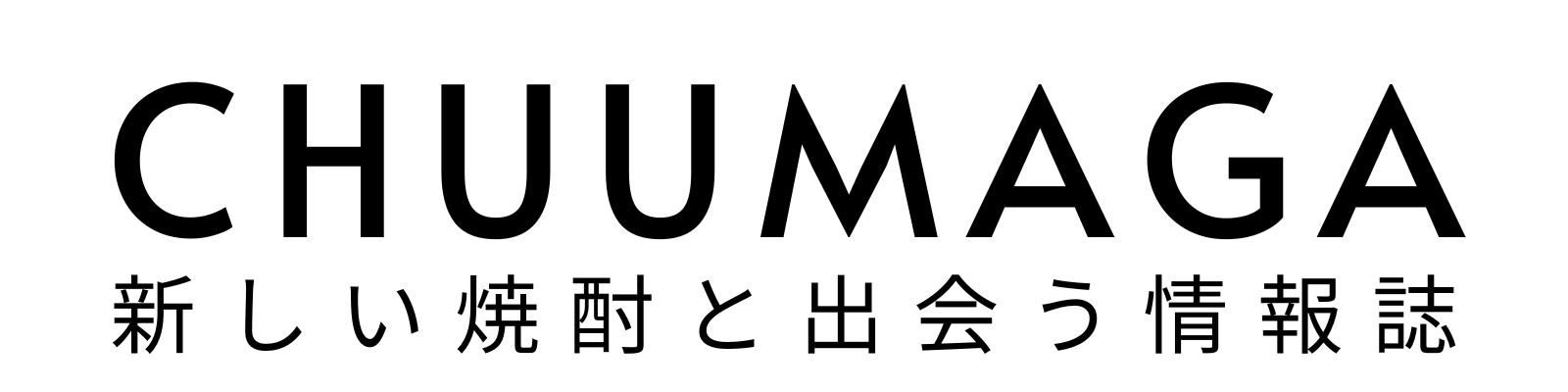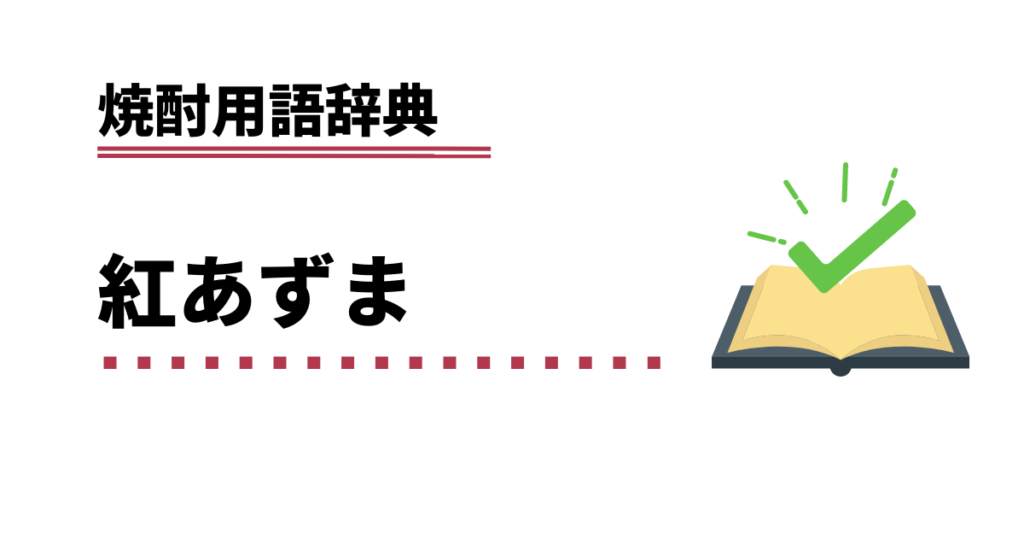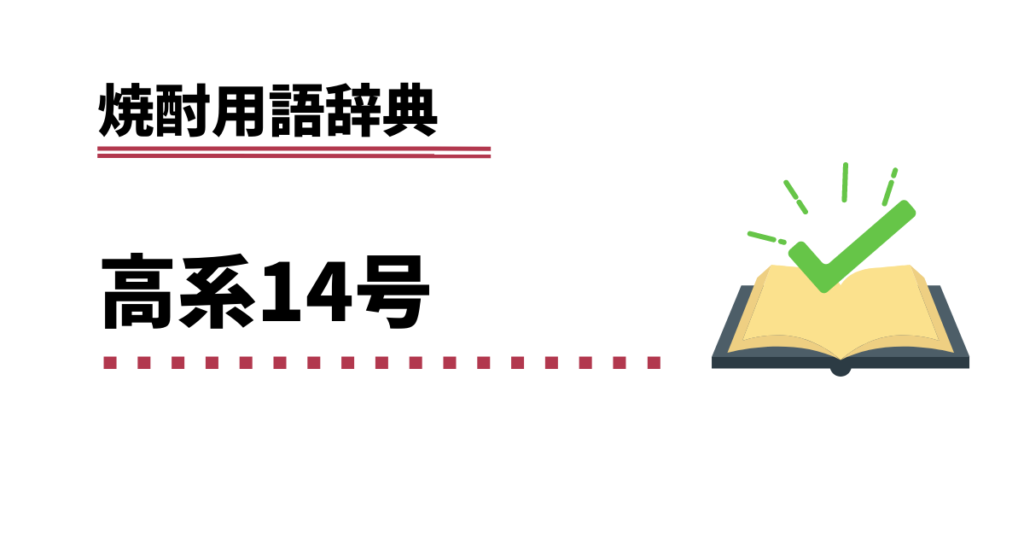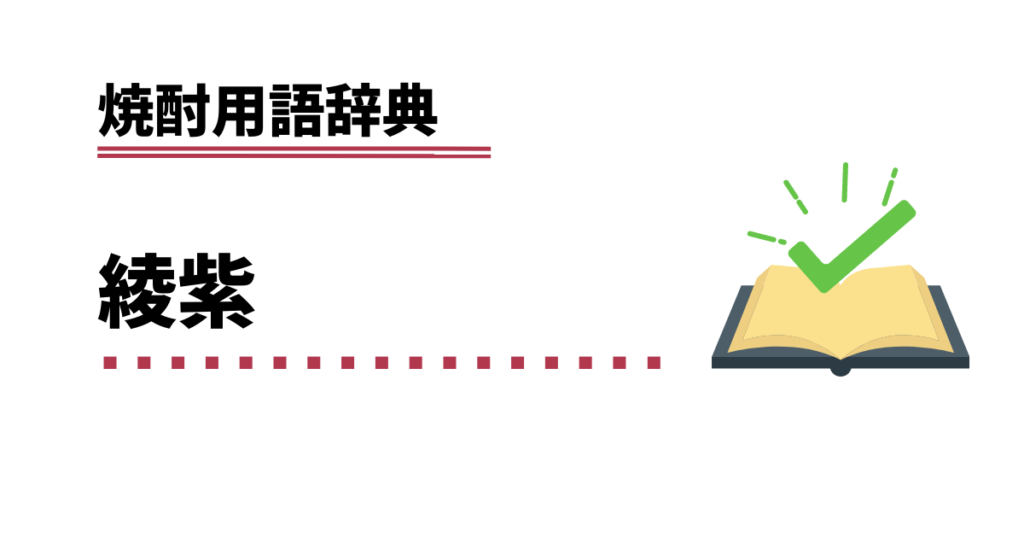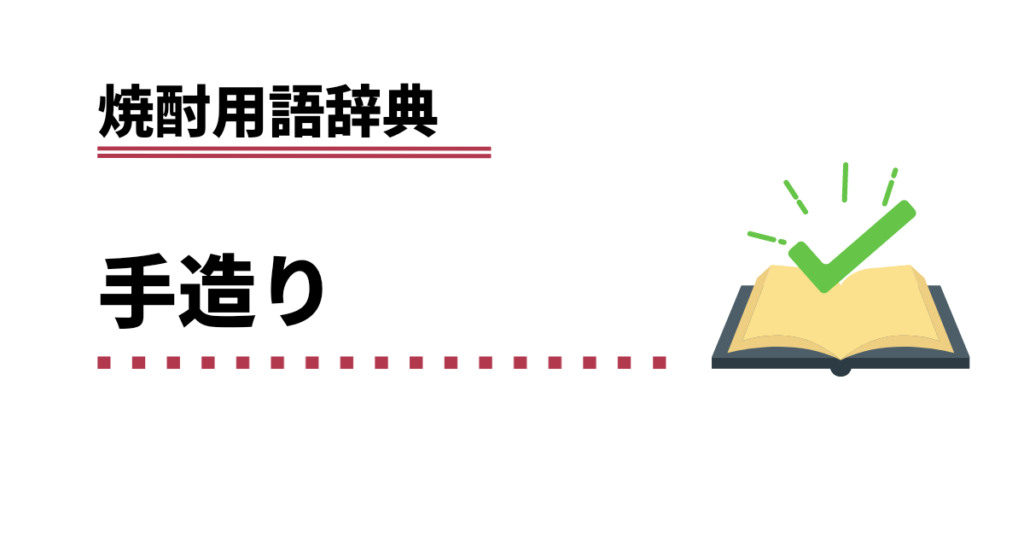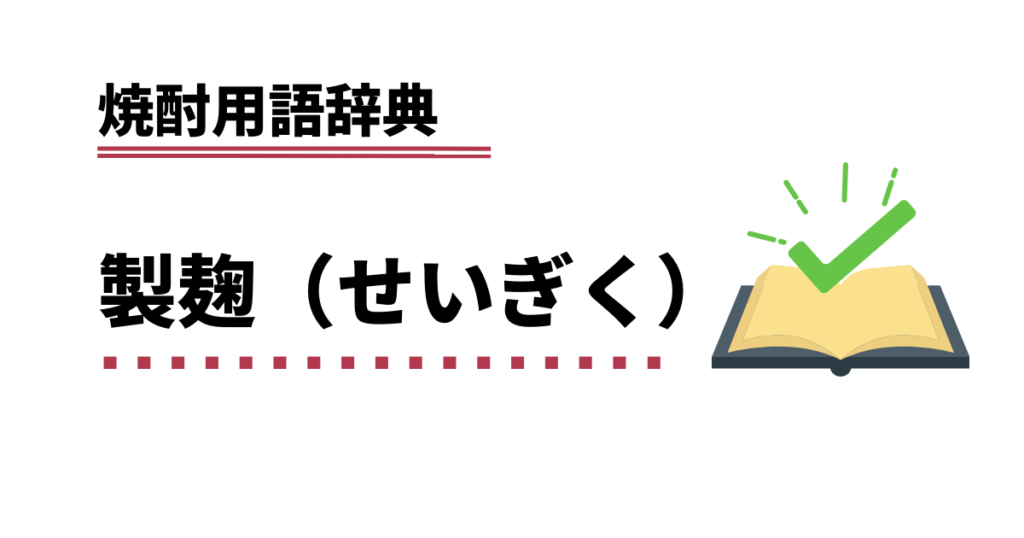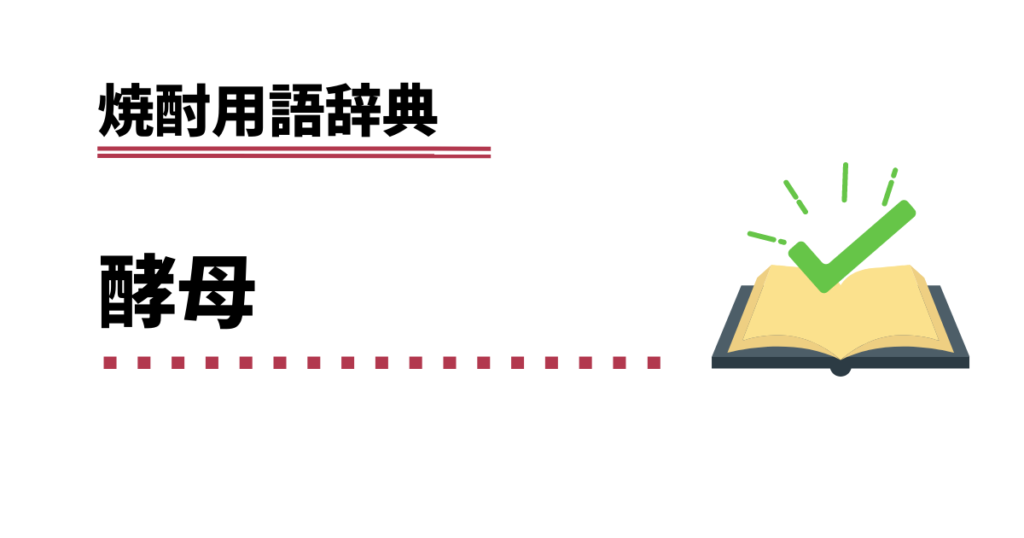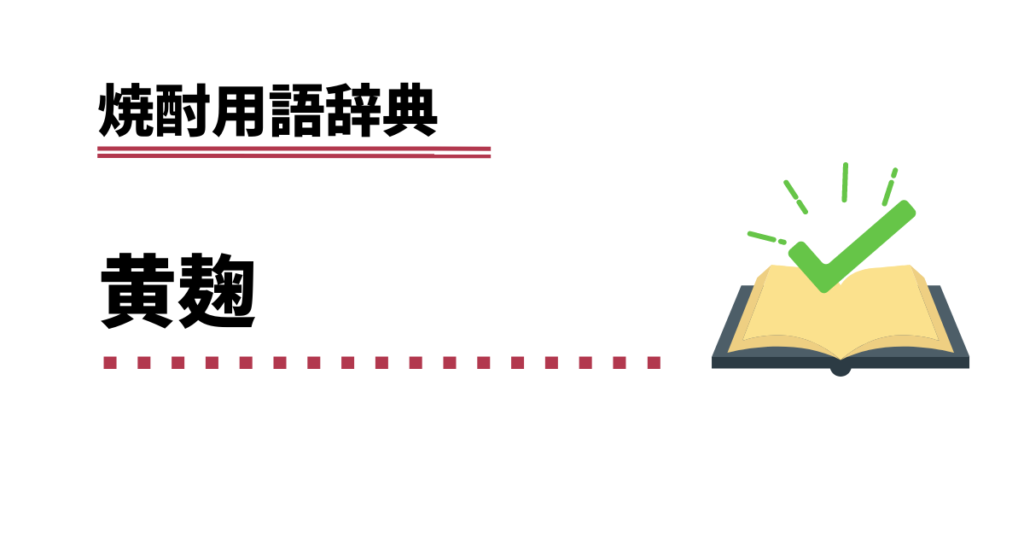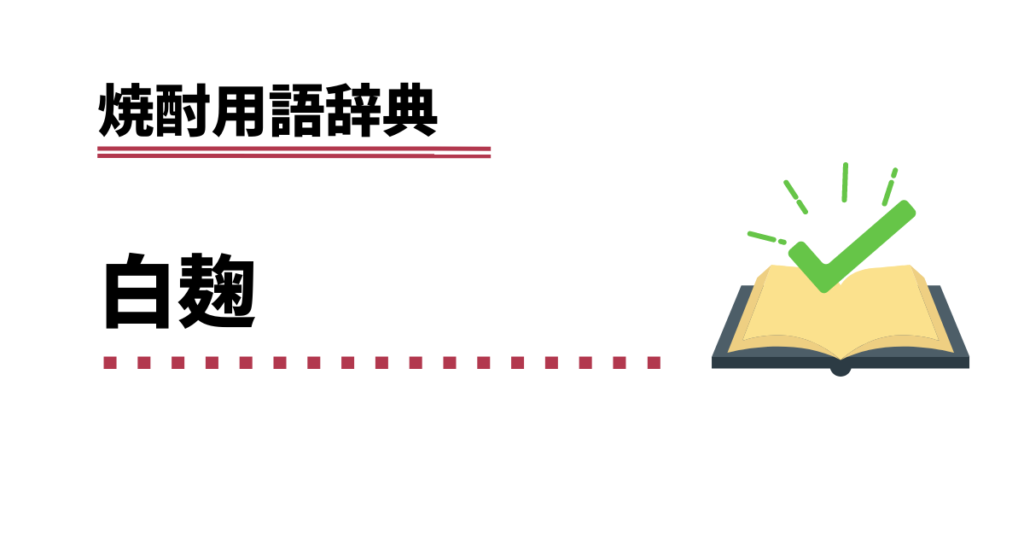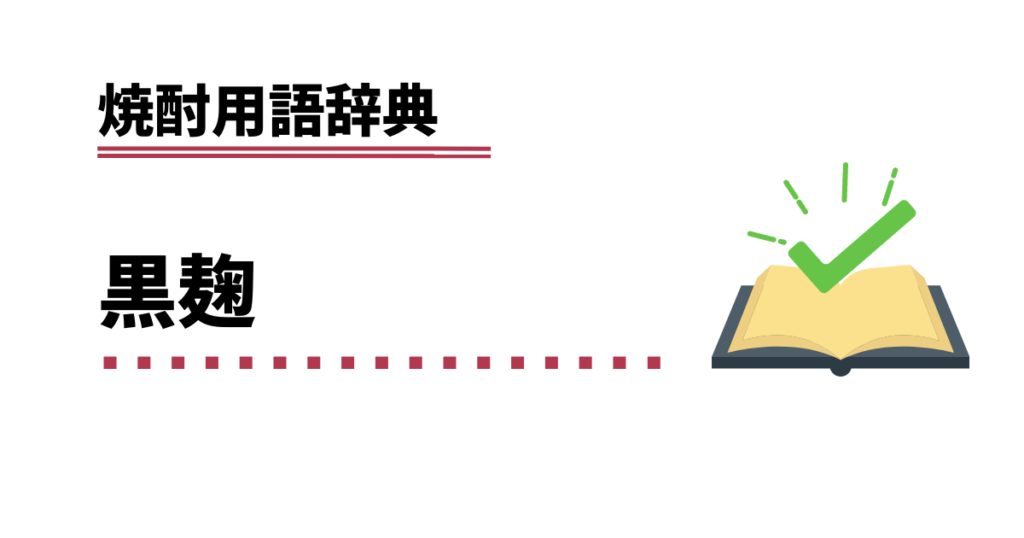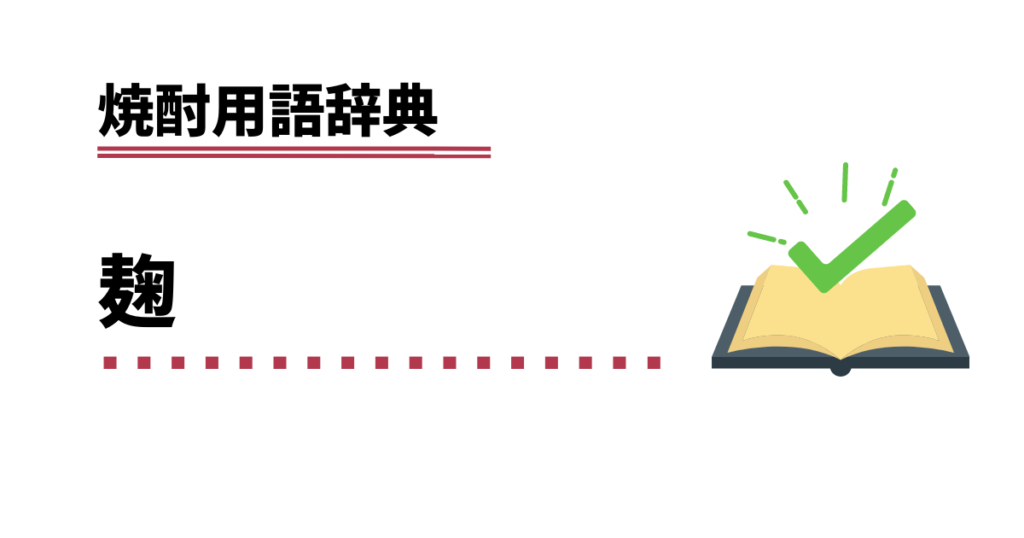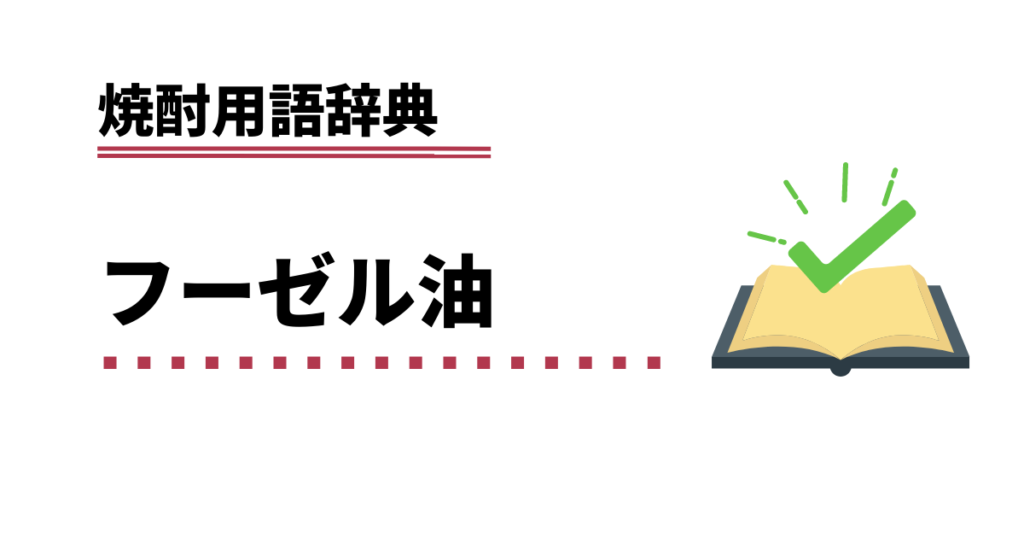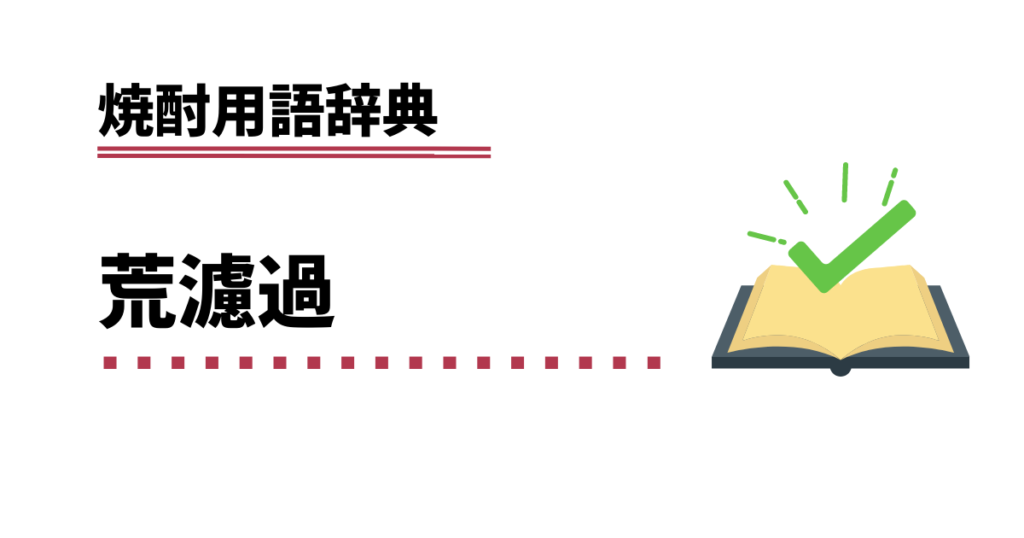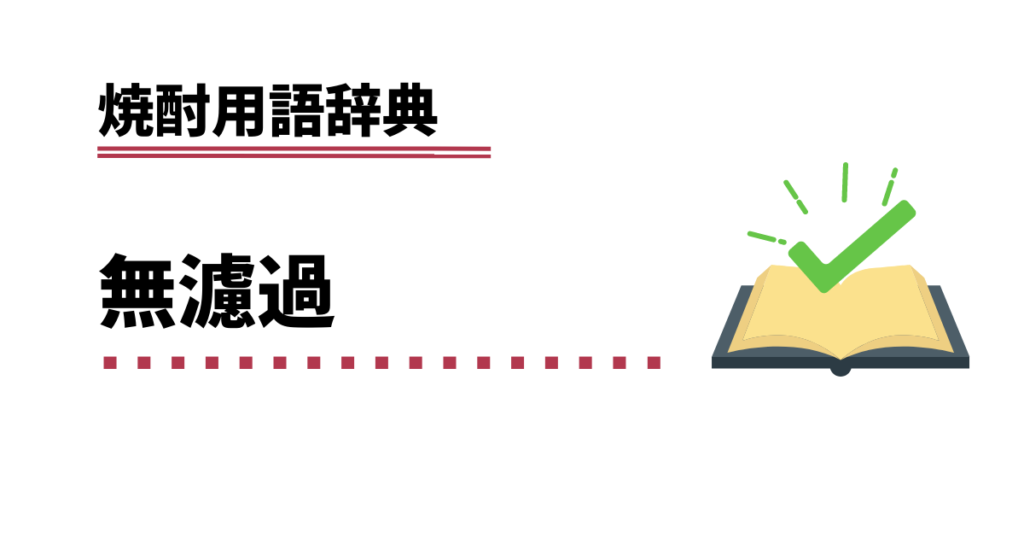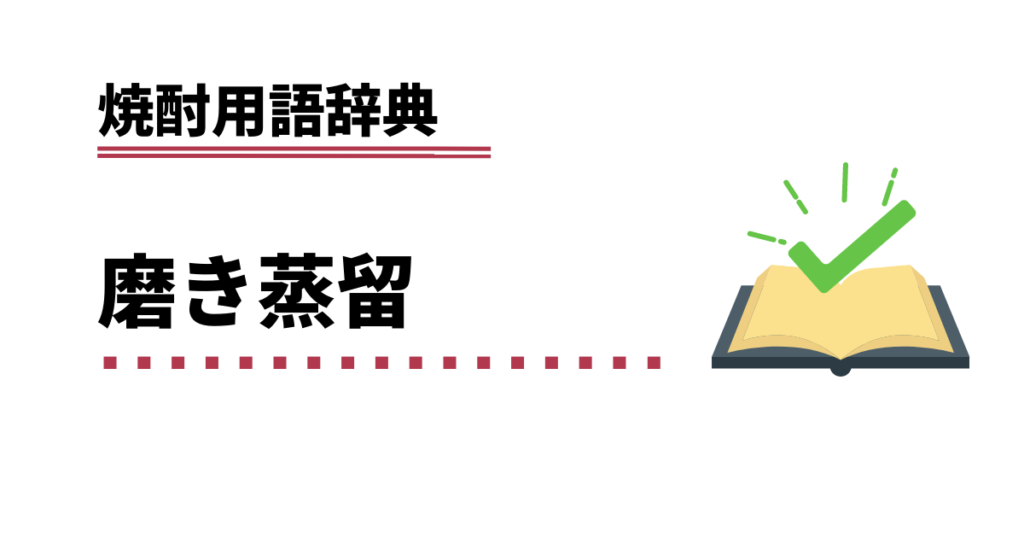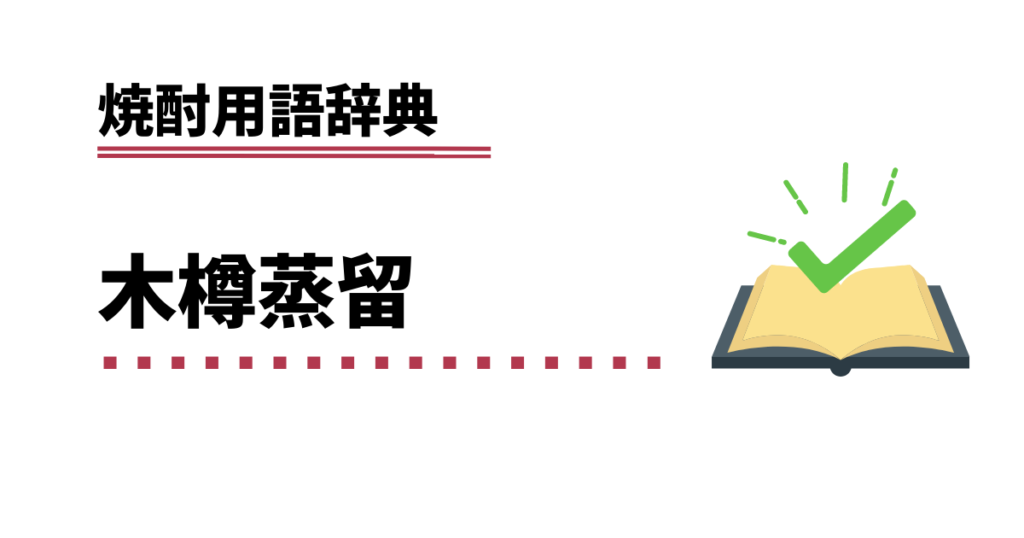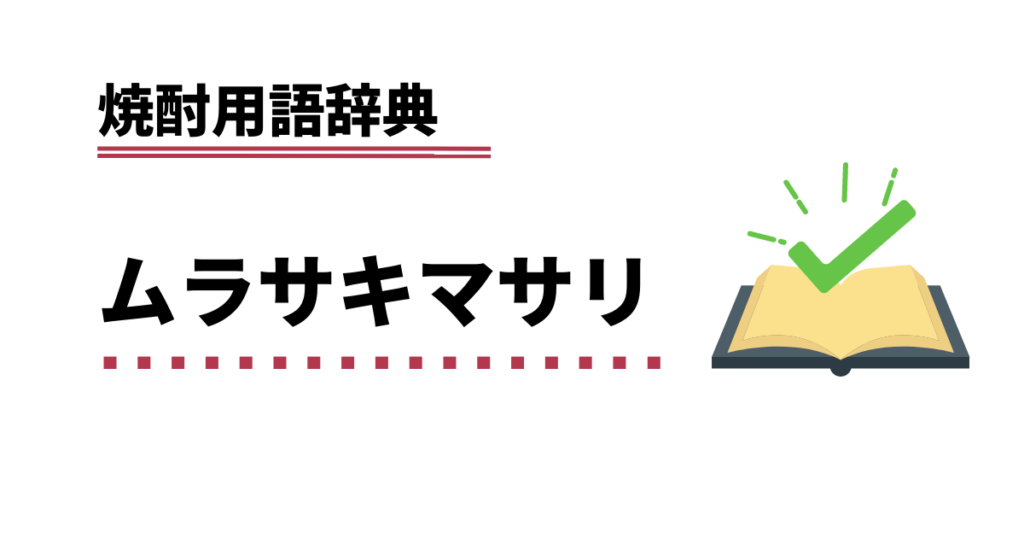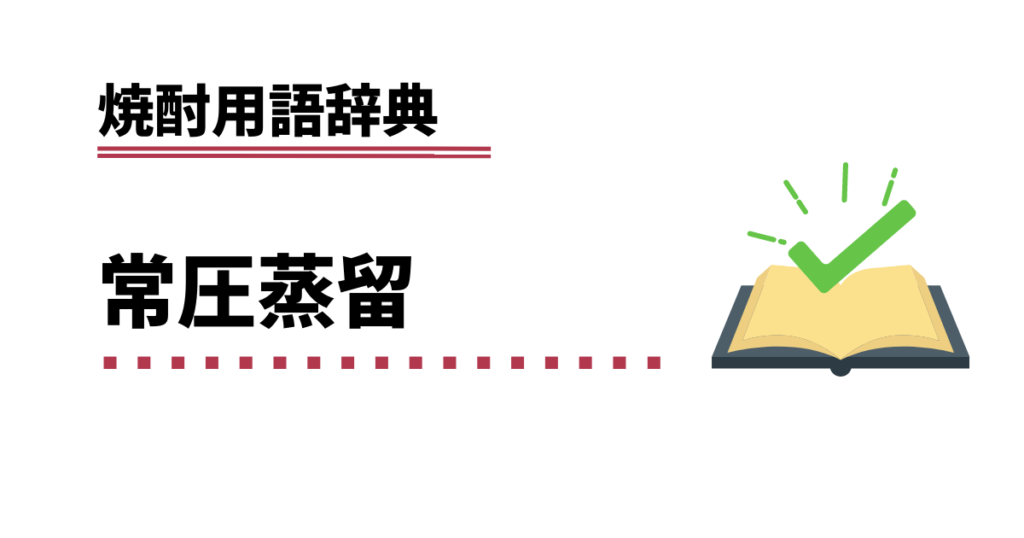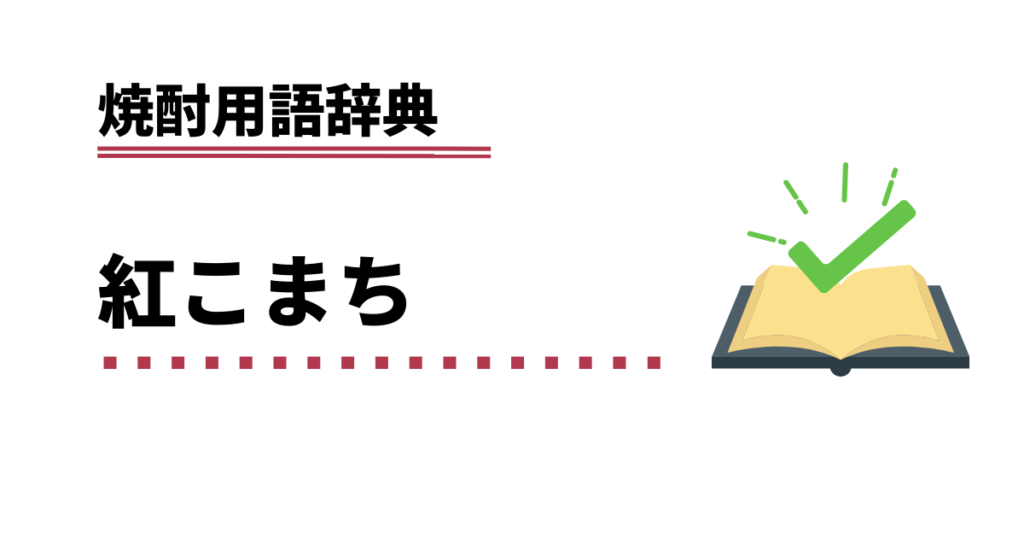用語辞典– category –
-

紅あずまとは
紅あずまとは、さつまいもの品種のこと。 ベニアズマ、べにあずま、紅東とも。 「関東859」と「コガネセンガン」の交配種である。 【特徴】 東の紅あずま・西の高系14号と言うほど収穫性と食味に優れていて、焼き芋にするとホクホク感とねっとり感を楽... -

高系14号とは
高系14号とは、さつまいもの品種のことで、「ナンシーホール」と「シャム」の交配種である。 【特徴】 東のベニアズマ、西の高系14号と言われるほど収穫量が多く、早掘りで知られる。 貯蔵性に優れており、貯蔵熟成後に焼くとホクホクした甘い芋に仕上がる... -

アヤムラサキ(綾紫)とは
アヤムラサキとは、さつまいも(紫芋)の品種の事。 「九州109号」と「サツマヒカリ」の交配種である。 【特徴】 紫系のさつまいもの中で最も発色がよく、加熱しても鮮やかな紫色を保つ。 ただしそのままでは食用には向かず、ほとんど甘みがない。 そのた... -

手造りとは
手造りとは、製麹の工程を機械を使わず手作業で行うこと。 ■製麹とは 麹菌を繁殖させる際の温度管理は38〜39℃という狭い範囲の温度帯をキープする必要がある。 この温度帯をキープするために機械を使うことも多いが、温度が上がりすぎたら手入れや自然換... -

製麹(せいぎく)とは
製麹(せいぎく)とは、穀類や芋類に麹菌を着床させ、麹を作る作業のこと。 その蔵によって細かい製法は違うが、具体的には以下のような手順を踏む。 ①蒸す:洗った後、吸水させた米などを蒸す。 ②種付け・種切り:種麹(あらかじめ麹を着床させたもの)を... -

酵母とは
酵母(イースト)は、糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物の総称。 酵母にはたくさんの種類の菌がおり、自然界には天然酵母として、ブドウ・米・麦の果皮などにそれぞれ違った酵母が、違ったバランスで生息している。 幅広く色々なものに使われて... -

黄麹とは
黄麹とは、穀類や芋類に黄麹菌を着床させたもの。 日本酒用麹とも言われ、古くから日本酒造りに使われていた。 始めは焼酎造りにも用いられたが、雑菌のケアが難しかった。 というのも、ほかの麹菌に比べクエン酸生成が弱く、殺菌効果が弱いという特徴があ... -

白麹とは
白麹とは、穀類や芋類に白麹菌を着床させたもののこと。 白麹菌は黒麹菌の突然変異種で、クエン酸の生成能力は黒麹同様高い。 白麹で造られた焼酎は、まろやかですっきりした丸みのある味わいの物が多い。 白麹菌の発見は、クセが強く飲みづらかった焼... -

黒麹とは
黒麹とは、穀類や芋類等に黒麹菌を着床させたもののこと。 クエン酸を良く生成するため、もろみ中の雑菌の繁殖を抑制するといった効果がある。 黒麹で造られた焼酎は、深く濃厚などっしりとした味わいであるものが多い。 日本酒造りに使用されていた黄... -

麹とは
麹とは、穀類や芋類などに麹菌が着床したもの。 麹菌はカビの一種で、米などに付着したものは、ふさふさした感じが見て取れる。 麹の語源は、「カビダチ(黴立)」が訛って「カウヂ」と変化したものとされている。 麹を作る過程のことを「製麹」という。 ...