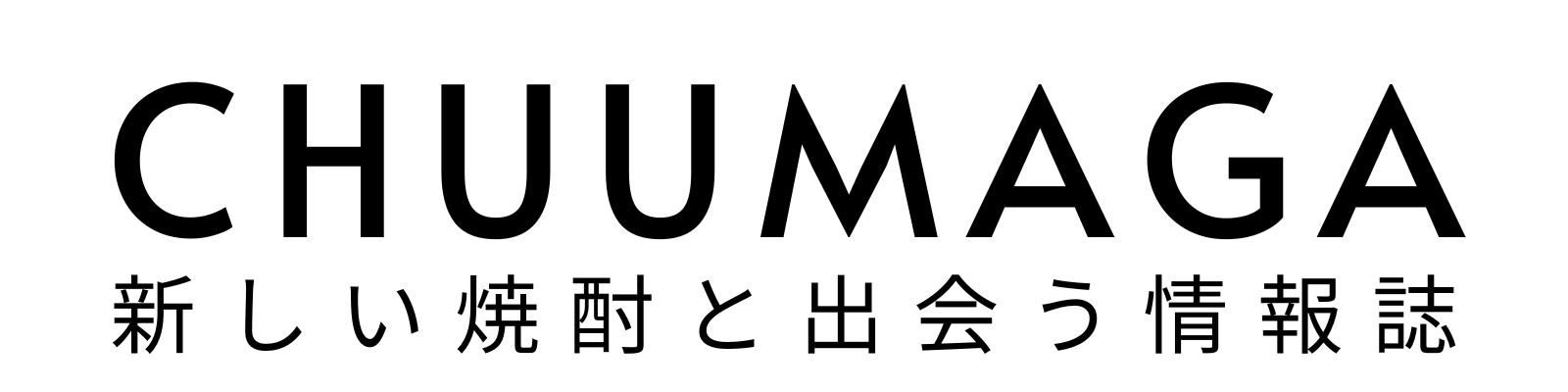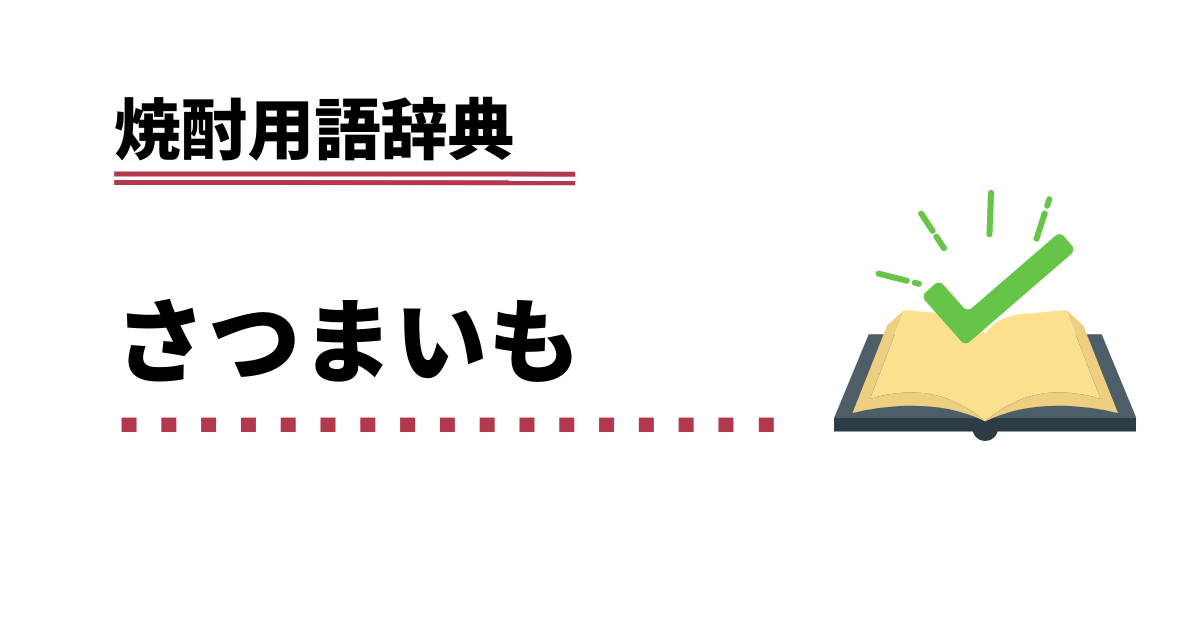さつまいもはヒルガオ科の植物で、根が肥大化したものが可食部となる。
日本へは中国から当時の沖縄に伝わり、鹿児島で普及した。このことから、薩摩の芋として「さつまいも」と言われている。
別名で甘藷(かんしょ)・唐芋(からいも)と言われる。
焼酎としての特徴
さつまいもを焼酎として使用すると、さつまいもの甘い香りはもちろん、重厚感のある香りが出やすい。
この重厚感こそが「クセが強い」と言われる所以で、苦手な人も多い。
ただ、乙類焼酎の中では最も銘柄の種類が多く、癖の少ないもの〜果物の香りがするものまで様々存在する。
ㅤ
種類
普通芋
食用として最も有名。果皮が紫で果肉が黄色い品種。
焼酎に使われると、さつまいも特有の甘い香りが楽しめる。
その品種名からか白芋と比較してのことか、紅芋や赤芋と表現されることもあるが、紫芋と混同してしまうため注意が必要。
紅〇〇という名前の品種が多い。
ㅤ■紅赤
紅さつまや鳴門金時などの銘柄は実は地方品種(その土地の風土に合った品種、ブランド名)であり、どちらも高系14号という品種が選別されたものでもある。
〜高系14号から派生したさつまいも〜
ㅤ■鳴門金時(徳島県)
ㅤ■五郎島金時(石川県)
ㅤ■坂出金時(香川県)
ㅤ■紅さつま(鹿児島県)
ㅤ■宮崎紅(宮崎県)
ㅤ■土佐紅(高知県)
ㅤ■大永愛娘(千葉県)
ㅤ■紅高系(千葉県・静岡県など)
ㅤ
紫芋
菓子によく用いられる。果肉が紫の品種。
焼酎にするとフルーティな甘い香りを放つ。
よく紅芋や赤芋とも表記されるが、紅芋はまた別の品種のこと。
また、普通種のさつまいもも、白芋と比較して紅芋や赤芋などと言われることもあり、混同しやすい。
品種名には紫が入っているものが多い。
ㅤ■ムラサキマサリ
ㅤ■アヤムラサキ
ㅤ■種子島紫
ㅤ■パープルスイートロード
ポリフェノールが豊富だが、それは「アントシアニン」という色素のこと。蒸留した焼酎に含まれる訳では無い。
もろみは麹菌が産生するクエン酸によって酸性であり、アントシアニン色素は酸性下で赤く変色する。そのため、仕込みの際もろみに紫芋を加えると、そのもろみは赤く変色する。
このことから紫芋で造られた焼酎は「紫」でなく「赤」と表記する銘柄も多い。
オレンジ芋
果肉がオレンジ色の品種。その色合いから人参芋ともいわれ、食べてみるとほんのり人参の香りがする。
焼酎にすると果物、紅茶、花のような香りが楽しめる。
ㅤ■ハマコマチ
ㅤ■ハロウィンスウィート
カロテンが豊富と言われるが、それは色素のことであり、焼酎には含まれない。
ㅤ
白芋
一般にはあまり見かけないが、生産量はかなり多い。果皮や果肉が薄黄〜白色の品種。
そのまま食べても粉っぽく甘みが薄い。
主に加工品に使われ、焼酎や片栗粉になる。それだけでんぷん質が豊富である。
焼酎に使われたときの特徴…というより、8〜9割の芋焼酎は白系の「コガネセンガン」という品種で造られているため、芋焼酎の味わいそのもののイメージを白芋が形作っている。
ㅤ■コガネセンガン
ㅤ■しろゆたか
ㅤ■こなほまれ
ㅤ
焼酎用の加工
通常さつまいもは収穫されてすぐに加工されもろみとなる。この際の加工は基本的にはさつまいもを蒸し、ふかし芋の状態にすることである。
ただし焼酎によっては蒸し芋とするのではなく、以下のように手が加えられることがある。
ㅤ■焼き芋
ㅤ■干し芋
ㅤ■磨き芋
ㅤ■吊るし芋
ㅤ■芋麹
いくつかの加工ではさつまいもの糖度をさらに引き上げるといった加工が見受けられる。
しかし当然ながら糖分は蒸留されないので、焼酎自体が甘くなる訳では無い。アルコール発酵を促したり、追加の香り成分を得るといった効果が大きい。
ㅤ
病気や害虫
さつまいもの作付面積は年々減少傾向にある。
農家の高齢化もあるが、病気の蔓延、中でも基腐病の蔓延が深刻な課題となっている。
■基腐病